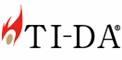自然時間と人工時間
今回は時間、
小学生に時計を教えるとき、
なんで1時間を100分にしないんだよ・・・って、
いつも思っています。(教えるのって大変なんです!!)
さて、時間・・・不思議な存在ですね。
その不思議を、ちょっと解明してみましょう。
まず、時間の単位について、
年・・・太陽の周りを地球が一周する時間(地球の公転)
月・・・地球の周りを月が一周する時間(月の公転)
日・・・地球が一回転する時間(自転)
この3つは、天体の動きを単位とした時間です。
自然時間です。
次に、週、時間・分・秒
これらは、人間が考えた時間の単位、人工時間です。
それでは、1週間はなぜ、7日なのでしょう。
そして、1日はなぜ、24時間なのでしょう。
1時間はなぜ、60分なのでしょうか?
1週間が7日なのは、
天動説当時、
地球と最も関係ある七つの天体
月・水星・金星・太陽(日)・火星・木星・土星
を一つのまとまりとしたのが始まりのようです。
たしかなことは解りませんが・・・?
昔の日本では、10日がひとまとまりでした。
古文の中にも
「十日あまり一日」とか「二十日あまり三日」などと
日付を表現しています。
ちなみに日本が7曜制を取り入れたのは、明治以降だそうです。
次に1日が24時間なのは、
昔の、12進法の名残り、
「日の出から日の入り」まで、「日の入りから日の出」までを
それぞれ12等分していたようです。
ちなみに日本は6等分、
12進法が起こったのは、
左手の人差し指から小指までの節(それぞれに3つあります)
(4本×3つで12)
を数えていたからではないかという説があるようです。
時間・分・秒で、60進法が取られたのは、
1から100までの数字の中で、最も約数が多いからとのこと、
約数が多いということは、細かく分けて扱いやすい。
つまり計算しやすいということで、自然科学の世界では重宝したようです。
中学生の作図の問題でも、「正六角形を書け」などがありますが、
円の半径で、円周を六等分して、「正六角形」を書きます。
6の倍数というのは、幾何学上、重宝していたのだろうな・・・
と思いますね。
以上のように、時間の単位について、まとめましたが、
自然時間は天体の動きですから、解りますよね。
実は、人工時間のの中でも「時間・分」は
商人たちの利息計算や費用計算などの必要性から生み出されました。
「時間は商人たちが他者を支配するための道具」(ジャック・ル・ゴフ)
となったわけです。
さらに、「時間・分・秒」は
科学者の時空座標上での実験計測の必要性から重視され、
現在の量子力学はさらに細かい時間の単位(プランク時間)を決めているようです。
このように、「時間・分・秒」は
科学の発達と、資本主義の発展に大きく関わってきました。
功利主義のベンサムは
「最大多数の最大幸福」という表現をし、
最もも多くの人たちに、
最も多くの富を与えることが幸福につながる・・・
と考えました。
最も多くの富を与えるためには効率アップが重要、
1時間内にどれだけの生産量を上げることができるか・・・
これが目的になり、
今、人間は人工時間に支配されるようになってきているのです。
関連記事